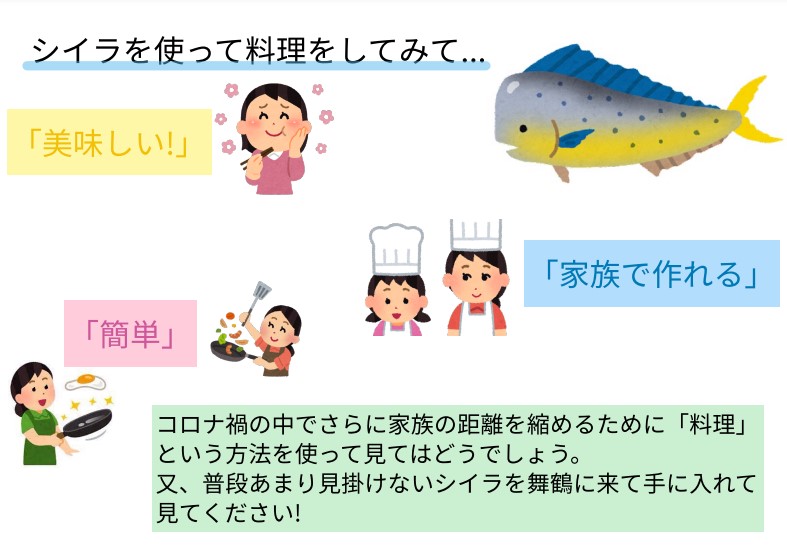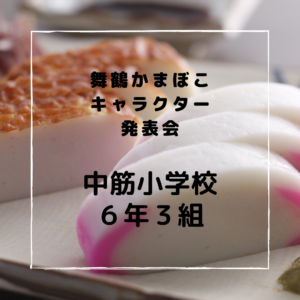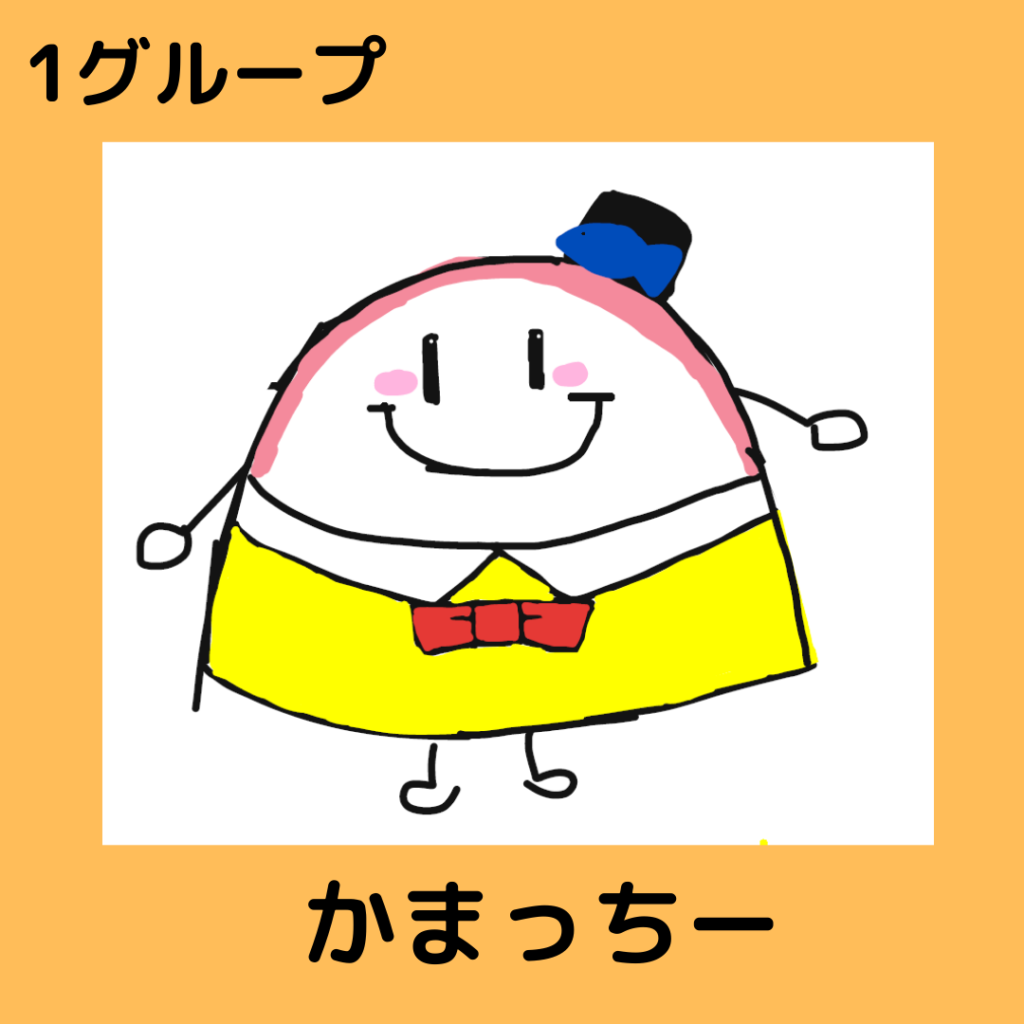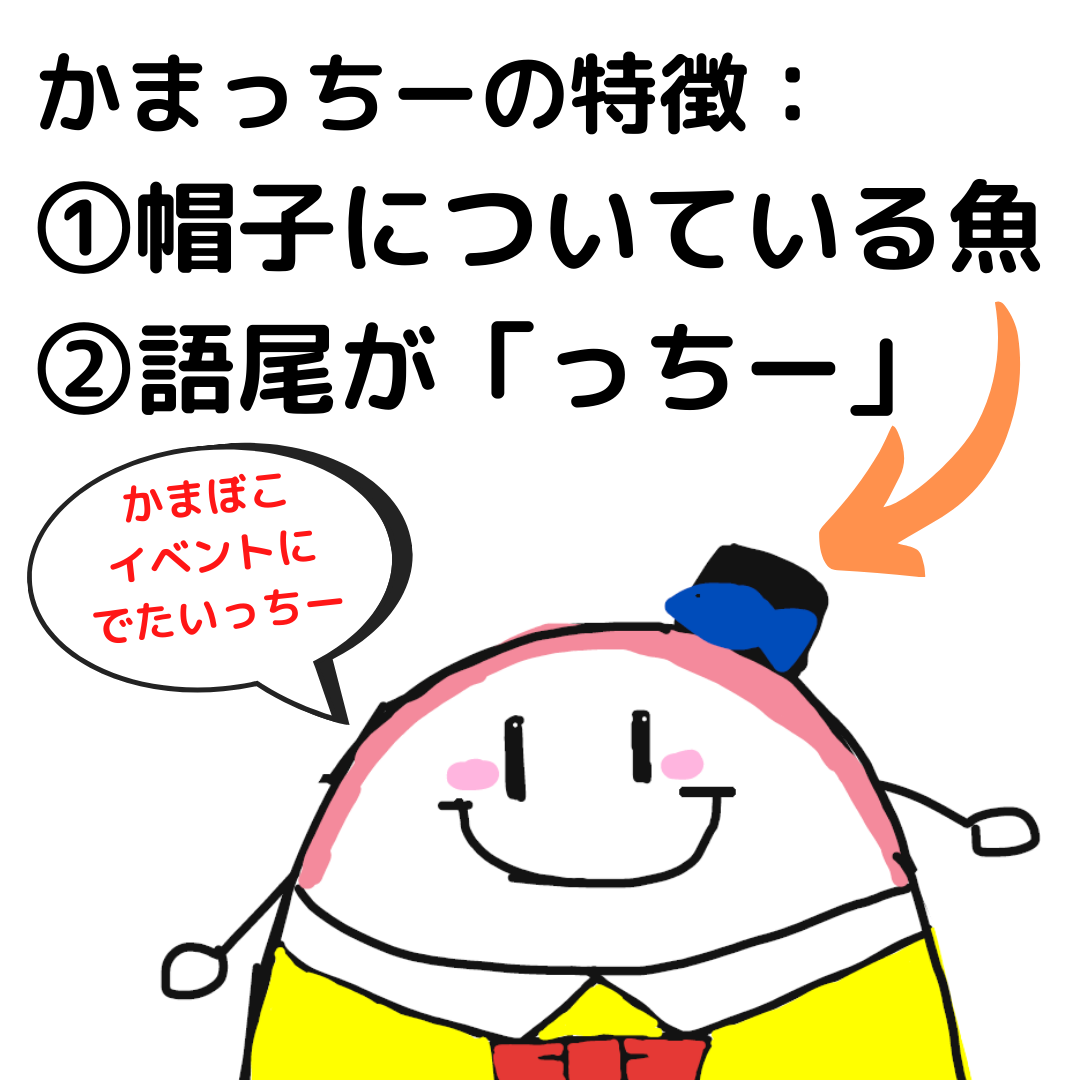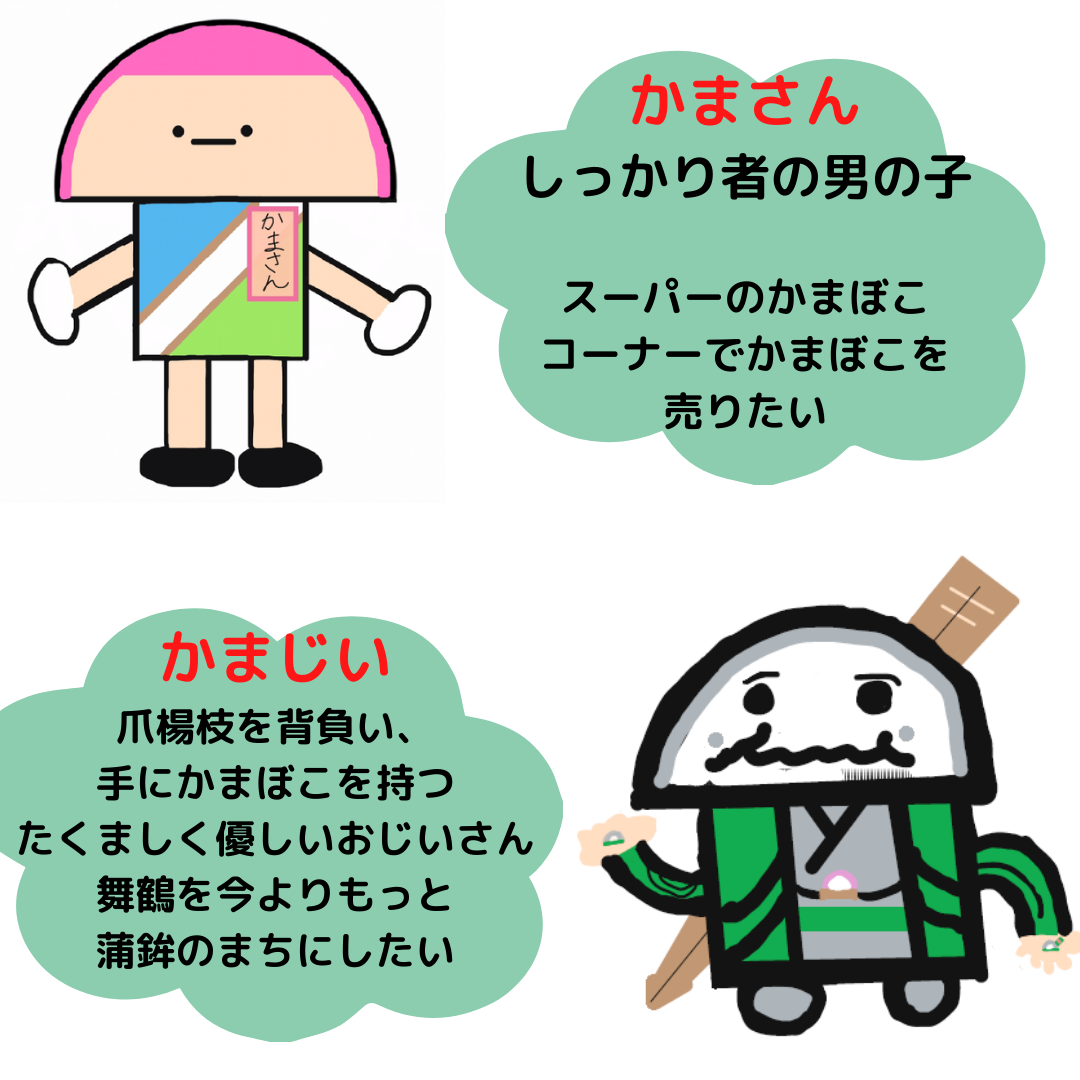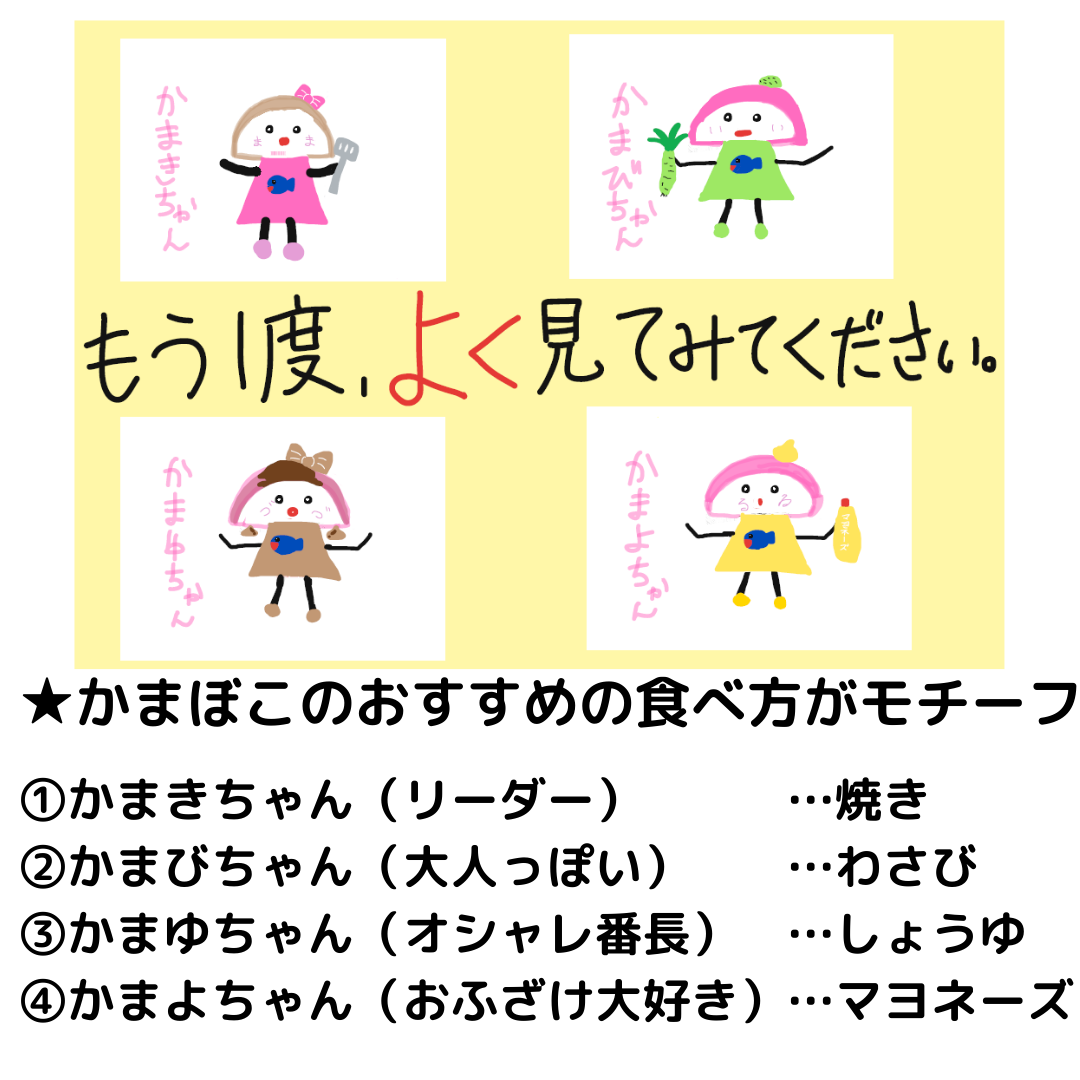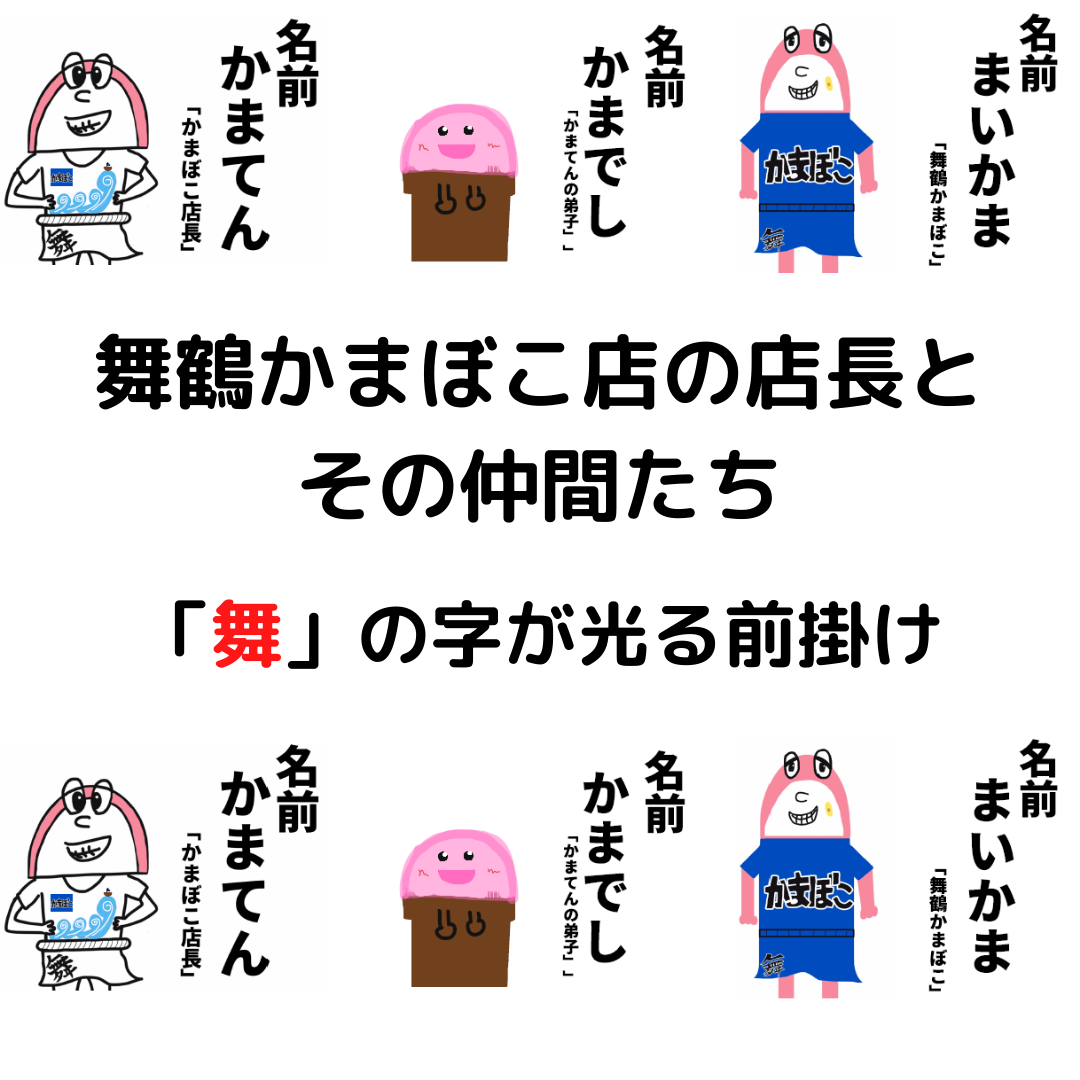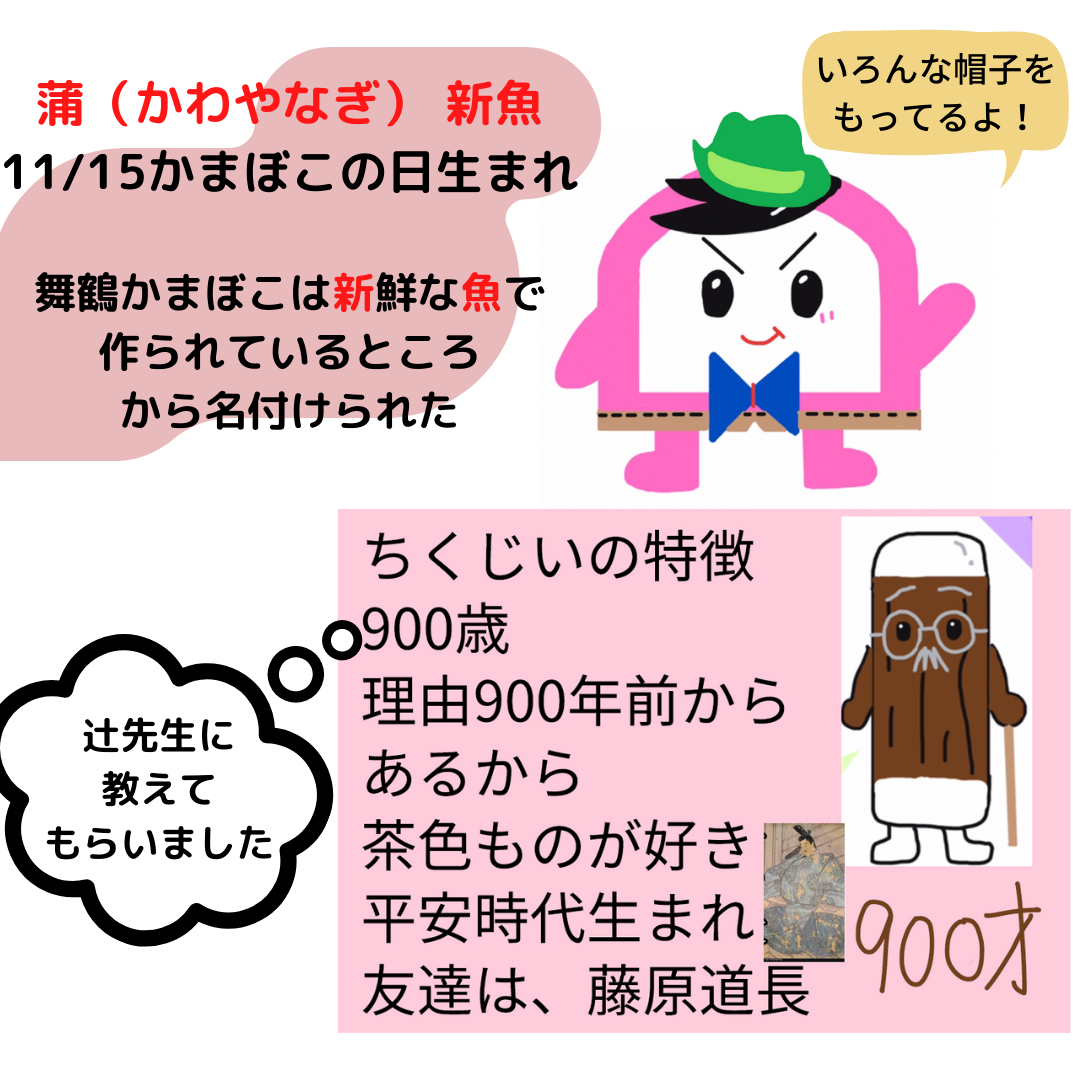かまぼこ博士のかまぼこ百科

「かまぼこ博士のかまぼこ百科」は、舞鶴かまぼこ協同組合の辻義雄専務理事(舞鶴市民から「かまぼこ博士」と呼ばれています。)が執筆され、2011年から約4年間にわたり、舞鶴市民新聞に連載されたものです。かまぼこ、とりわけ舞鶴かまぼこへの愛に満ちた「かまぼこ博士のかまぼこ百科①~㊺」を順次掲載します。読めばあなたも「かまぼこ博士」。そして、舞鶴かまぼこがとても食べたくなってしまうでしょう。
なお、当コラムに掲載するにあたっては原文のままとし、日時や役職、社名等も当時のままとしています。また、今では存在しないメーカー、商品もありますのがご了承ください。
商品紹介 「調味すり身」丸海食品謹製
当初は、すりみを加熱して製品として出荷している煉製品業者にとって、その素材であるすりみを生でそのまま消費者に提供するという思い切った発想で商品化したものが、この調味すりみシリーズであり、丸海食品㈱が製造している。社長は 若村和重氏(昭和14年生まれ)であり、今や組合員の中では最長老となった。
魚肉は、すりみにすると、普通は“すわり”という現象をおこして、元々すりみが持っていたねばりと加熱したときに弾力をつくる能力がそこなわれてしまう。(タンパク質が変性をおこすからである。)
ある程度の時間が経過しても、“すわり”の現象の進行を抑えて、家庭ですりみを料理素材として活用していただくというのが当初の目的であった。
“すわり”現象にすりみがやられないうちは、野菜と混ぜ合わせたりして、油で揚げれば、アツアツの野菜天ぷらの味を楽しめたりするのだろうが、この商品は、あくまで“鍋”をターゲットにしており、このままの形で、鍋の中に落すと、工場でできあがったばかりのつみれの味も楽しむことができる。
関西地区は、関東地区と比較すると、このつみれを食べる習慣が少なかったが、最近、鍋もいろんなものができて、その味付けも、鍋に入れる素材もバラエティに 富むようになった。
従来の和風のものから、中華風、洋風、エスニック風と味そのものも色々と楽しめるようになった現在、その中に入れる具材の種類もどんどん増えてきている。
調味すりみシリーズでは、イワシ、アジのような色はやや黒いが、旨みの強いすりみもあり、タイやハモのように、淡白だが色の白いすりみもあり、寄せ鍋をしても、それぞれの魚の味がして、美味しい。
なによりも、魚の骨を取る必要もなく、そのまま丸ごと食べれるというのもありがたい。
特に赤身の調味すりみには小骨がまるごとすりつぶされて入っているので、無理なくカルシウムも多く摂取することができるので、育ち盛りの子供にはたくさん食べさせてあげたい。
我が家でも、寒い冬の鍋料理には欠かせないアイテムとなっている。
こうした調味すりみは、多少、ねばりと弾力を失ってタンパク変性を起こしているので、鍋に入れて加熱をすることで、かえって繊維がばらけたような状態になり、ちょうどカニ身のような状態になり、中に出汁をたっぷり含んでくれるので、これはこれで、考えようによっては美味しい。
一時は、絞りだしの袋に入れて、家庭で鉄板の上に絵や文字を絞り出し、焼いて食べる子供向けの遊びのような商品も開発したこともあったが、残念ながら定着することはなかった。
かまぼこ屋さんたちのアシ (=弾力)を重視する考えからは、こうした商品はうまれなかったのかもしれない。
実は、生すりみをこのような形にして、チルドで流通させたのは、おそらく丸海食品が日本初であった。商品を発売してから、単品で1億円商材になったこともあり、当時は、久しぶりに舞鶴からヒット商品が生まれたと大喜びしたのであった。